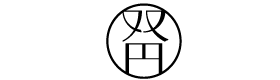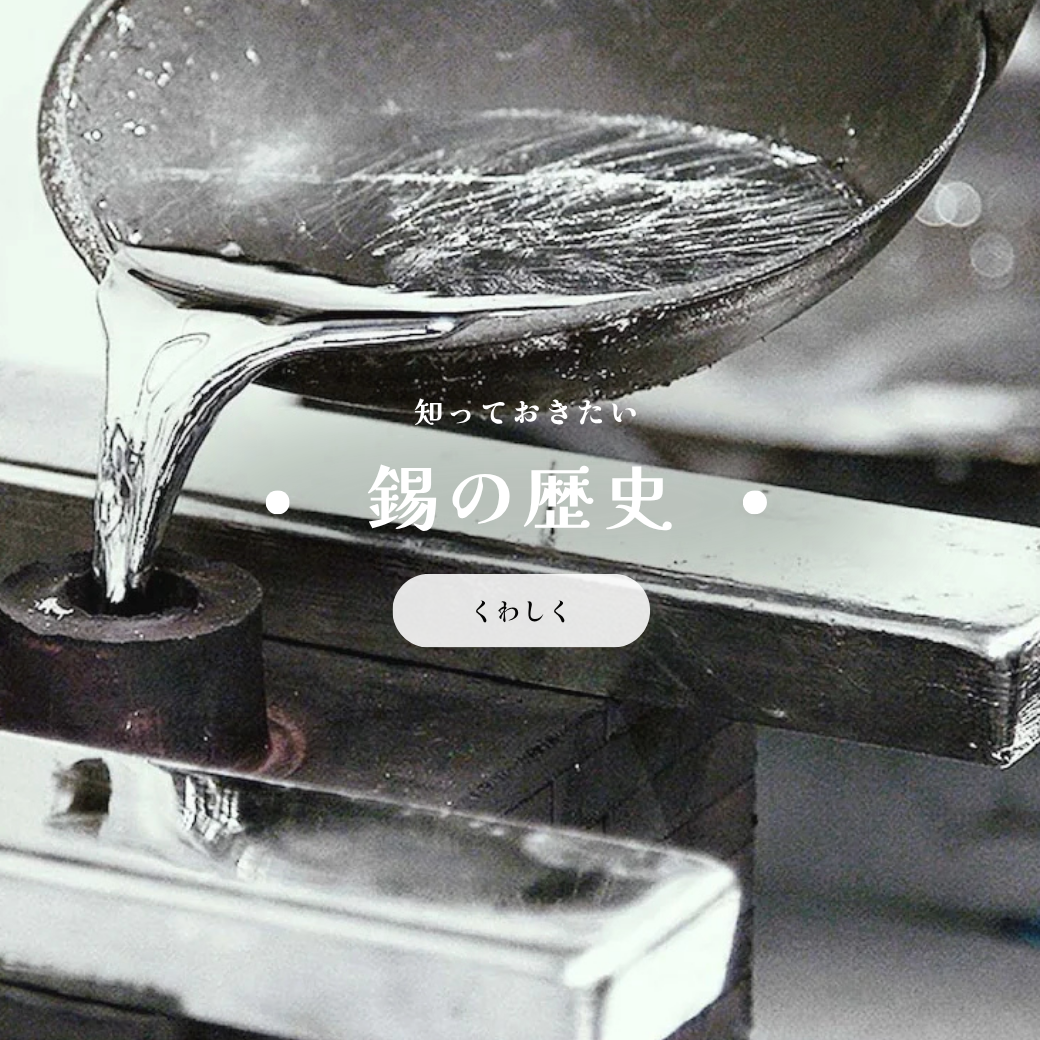ガラスの歴史

「光をかたちにしてきた─ガラスの歴史」

ガラスとは、光を通す素材です。その性質ゆえに、古代の人々はそこに特別な魅力を見出しました。
現代的な素材と思われがちなガラスですが、その始まりは驚くほど古く、紀元前3000年頃のメソポタミアやエジプトでは、すでに装飾品としてガラスが用いられていました。
やがて、紀元前1500年頃には、コアガラス技法と呼ばれる製法が生まれ、容器としてのガラスが作られ始めます。光を宿すこの素材は、装飾から道具へと役割を広げながら、文明とともに歩みを進めていきました。

東の果て、日本にガラスが本格的に姿を現すのは奈良時代。東大寺の正倉院には、ペルシャ産のガラス器が今なお保管されています。遥かなシルクロードを越えてもたらされたそれは、異国の光とともに、当時の人々の目にどれほど鮮やかに映ったことでしょう。
さらに時代が下り、江戸時代には、日本独自の美意識がガラスに命を吹き込みます。「江戸切子」はその代表であり、夜の行燈の灯りに照らされた切子のきらめきは、庶民の暮らしに小さな幻想をもたらしました。ここでも、ガラスは光と結びつくことで、心を豊かにする存在となっていったのです。

19世紀末、ヨーロッパではガラスに新たな風が吹き込みます。きっかけは、日本から届いた浮世絵──その大胆な構図や、淡く重なる色づかいにインスピレーションを受けた西洋の芸術家たちは、ガラスを絵画のように扱い始めました。アール・ヌーヴォーの巨匠たちは、ガラスに光と色のゆらぎを表現し、見る者に詩的な印象を与える作品を生み出します。また、ステンドグラスも宗教的な象徴を越え、自然や物語を描く「光の絵画」として新たな役割を担うようになりました。
ガラスは、人類の歴史の中で常に「光をかたちにする」素材として進化してきました。その透明な肌に光を宿し、ときにまばゆく、ときに幻想的に世界を映し出すガラス。その変幻自在な美しさは、今も私たちの感性を照らし続けています。