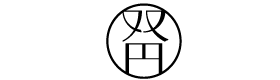記事: けやきの歴史
けやきの歴史
「堂々たる木、欅の話」

欅(けやき)は、日本の風景にしっくりとなじむ木ですが、実は「見事」「際立って美しい」という意味の「けやけし」から名付けられたとも言われています。その名の通り、まっすぐで力強く伸びる姿は、神社の御神木としても多く使われてきました。

江戸時代には、欅の木目の美しさと耐久性が重宝され、大名屋敷の玄関や仏壇、さらには太鼓の胴にまで使われていました。特に大きな一枚板は「欅の一枚板」として高級品とされ、今でも古民家の座卓や看板に使われることがあります。

面白いことに、欅はその香りでも知られており、加工中は独特の甘くスパイシーな香りが立ち上がります。木工職人の中には「この香りを嗅ぐと、背筋がしゃんとする」という人も。
古くから人々に愛されてきた理由が、姿形だけでなく香りや手触りにも宿っていることを感じさせます。