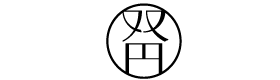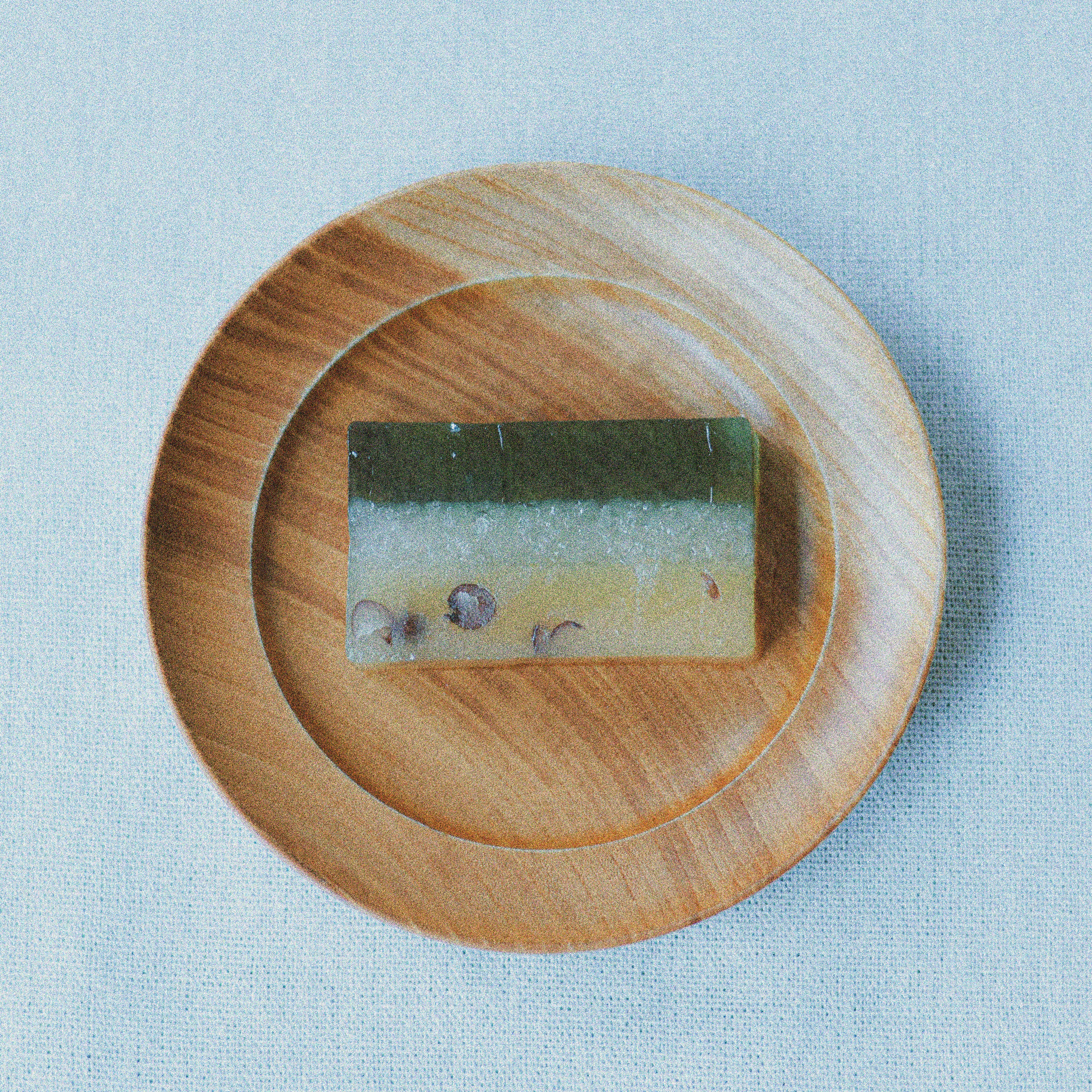商品一覧 漆工房大島
おわん けやき / クリアー
セール価格¥5,720
タンブラーM けやき / クリアー
セール価格¥11,550
平皿S けやき / クリアー
セール価格¥4,400
平皿XS けやき / クリアー
セール価格¥3,850
タンブラーS けやき / クリアー
セール価格¥8,580
記念商品 平皿S けやき / クリアー
セール価格¥8,500
平皿M けやき / クリアー
セール価格¥6,380
おちょこ けやき / クリアー
セール価格¥3,520
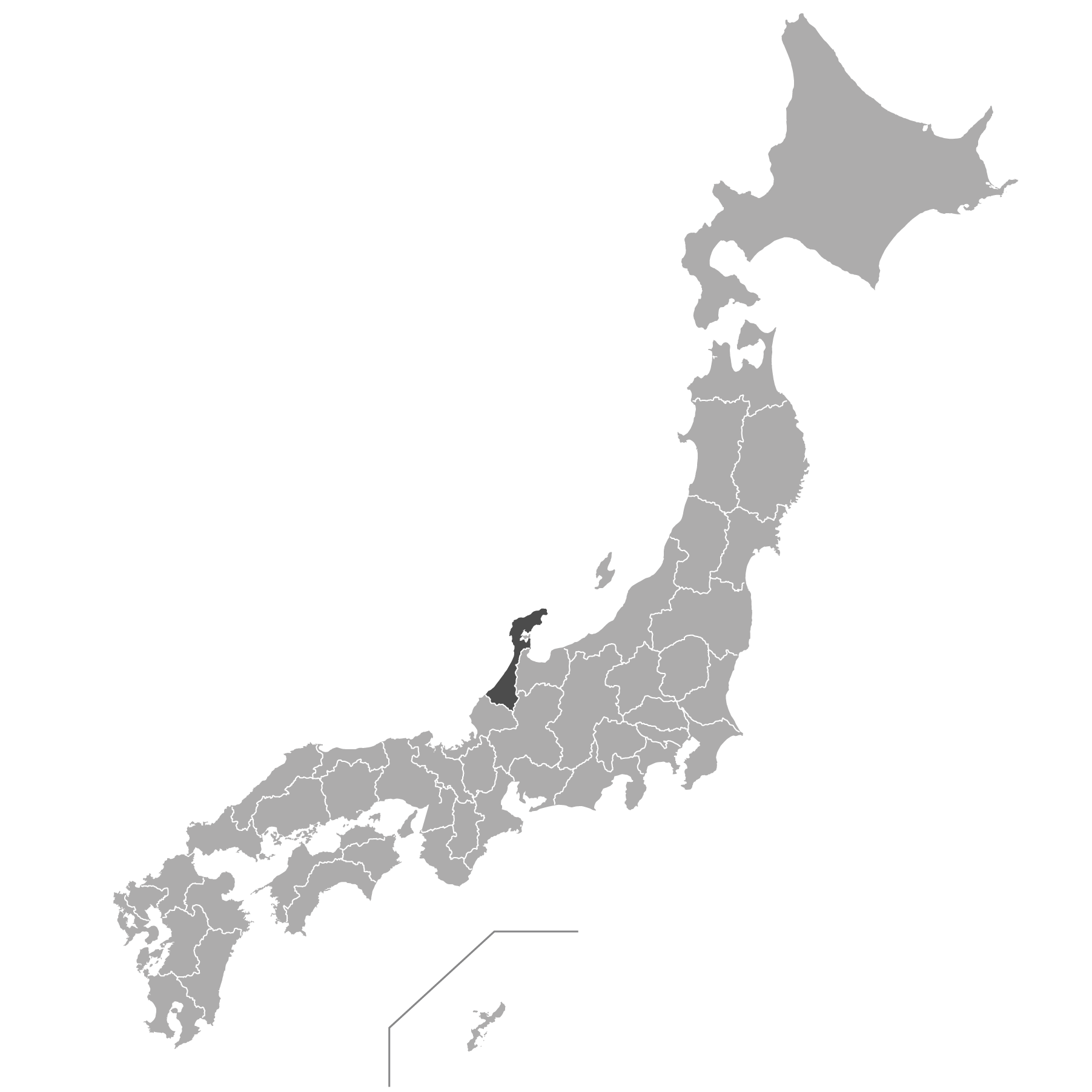

芭蕉も愛した温泉地の名漆器 /

漆器の屋台骨「木地の山中」 /

美しきタフネス、その理由 /


縁をつくるギフト
贈り物選びは双円