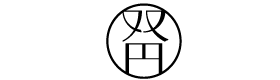記事: 錫の歴史
錫の歴史
「柔らかくて、粋。日本と錫のはなし」

金属といえば硬くて冷たいもの——そんなイメージを裏切るのが、錫(すず)です。指で少し力を加えるだけで曲がるほど柔らかく、手に取るとどこか温かみを感じる金属。
日本では古くから、茶器や酒器、仏具など、日常と儀式の間をつなぐ「粋な道具」として使われてきました。

日本で錫が本格的に使われ始めたのは、奈良時代(710〜794年)。正倉院には、錫を使った容器が今なお保存されており、当時の貴族たちが薬や香料を入れて大切に使っていたことがわかっています。

さらに時代を下って、室町時代の文献(15世紀頃)には、錫製の茶器が登場します。戦国大名の中には、わざわざ中国から錫器を取り寄せた記録も。格式と実用性を兼ね備えた「通の道具」として、茶の湯の世界でも愛されました。
江戸時代に入ると、庶民にも錫製の酒器や皿が広まり、「錫で飲む酒は旨くなる」と噂に。錫はとても安定した金属で、水や酒に成分が溶け出すことはほとんどありません。味が変わる理由には科学的な裏付けがまだはっきりとはないものの、においのもとになる物質をわずかに吸着する可能性や、熱がすばやく伝わる性質が、酒の香りや温度に心地よい影響を与えているのでは――そんな意見もあるのです。
千年を超えて使われてきた錫。時代を越えて人々に選ばれてきたのも、納得のいく不思議な魅力がある素材です。